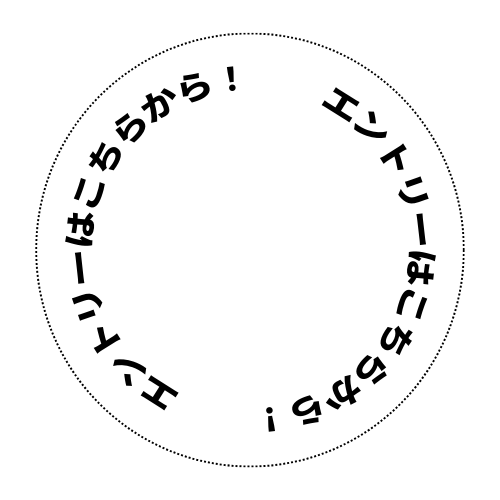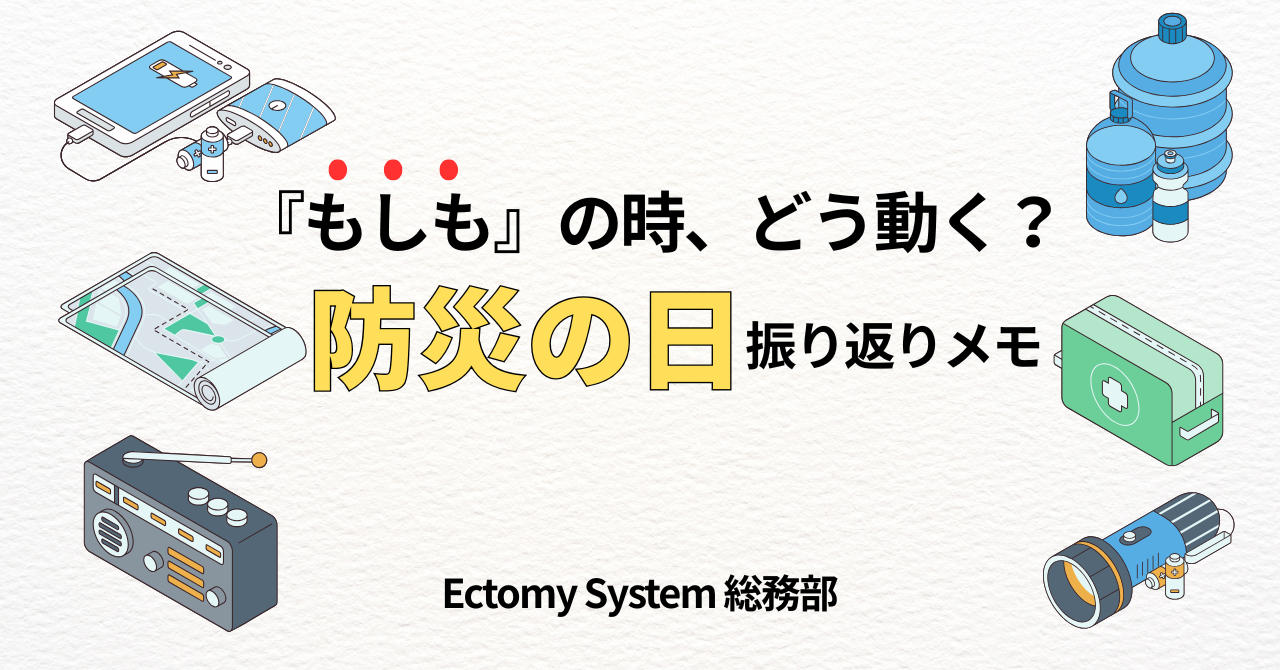目次
9月1日は「防災の日」
改めて“備え”について考えるきっかけになる日です。
毎日仕事や生活に追われていると、
「いつかやらなきゃ」と思いながらも、防災対策って後回しになりがちですよね。
正直、私もそうです。
防災のために日頃から準備しておくことも大切ですが、
“いざというときの自分や家族の行動を、イメージできるかどうか”
ということも大事なのかもしれません。
備えって、何から始めたらいいんだろう?
防災対策って言っても、やることはたくさんあって、最初はちょっとハードルが高く感じます。
でも「完璧にやる」よりも「できることを、できるときに」が大事。
たとえば、こんなことから始められます⇩
○ 家に飲み水と食料を3日分置いておく
○ モバイルバッテリーをフル充電にしておく
○ スマホの緊急速報通知をオンにしておく
○ 家族と「連絡がつかないときの集合場所」を話し合っておく
○ 懐中電灯やラジオ、どこでもトイレなどの最低限の防災グッズをまとめておく
全部いっぺんにやれるといいのですが、
「今週は食料品だけでも見直そう」みたいなペースでも十分だと思います。
防災グッズ 見直してみたら・・・
私自身も、防災の日をきっかけに久しぶりに家の中を見直してみました。
○ レトルトごはん → 賞味期限切れ
○ 水 → 期限近し
○ 懐中電灯 → 電池切れ
○ モバイルバッテリー → 半分くらいの残量
…というわけで、「備えてるつもりだったけど、備えてなかった」状態に気づきました。
特に乾電池や食品系は「気づいたら切れてるもの」ランキング上位常連です。
これを機に、小さなチェックリストをスマホメモに作りました(やる気になってるうちに…!)。
災害が起こるとき私はどこにいるんだろう?
地震も台風も、自分で選んだタイミングでは起きません。
だからこそ、
○ 通勤中だったらどうする?
○ 出先にいたら家族とどう連絡をとる?
○ 家に帰れないとき、どこに泊まる?
○ 一緒に暮らしている猫は、どうやって避難させる?
…など、「いつもと違う場所にいるときの行動」を想像して、
災害が起きたときの行動をシミュレーションしておく
災害時に“考える余裕”はないからこそ、
何も起きていない今、考えておくことに意味がある。
そんなことを今回、改めて感じました。
防災って自分だけの話じゃない
最近では「自助・共助・公助」という言葉が防災でも使われます。
自助:一人ひとりが自ら取り組むこと
共助:地域や身近にいる人どうしが一緒に取り組むこと
公助:国や地方公共団体などが取り組むこと
3つの連携が円滑なほど災害の被害が軽減できるそうです。
当たり前のようでいて、
災害時に一番頼りになるのは「自分の備え」と「近くの人との助け合い」です。
近所の人と挨拶するだけでも、非常時には心強くなるかもしれません。
おわりに:考えるだけでも一歩前進
「備えなきゃ」と思いながら手をつけられていない方、
「うちはもうできてるよ」という方、
「何からやればいいのかわからない」という方も、
このタイミングで一度、
防災についてふと立ち止まって考えてみるのはきっと意味があることです。
完璧じゃなくても、できるところから始めて
万全の準備ができるよう取り組んでいきたいと思います。